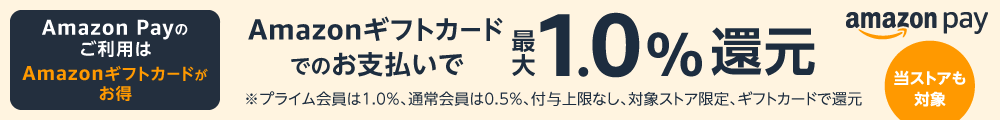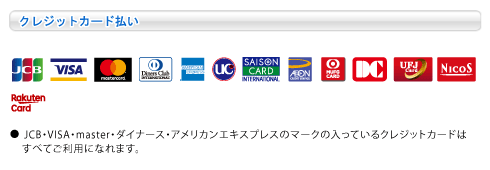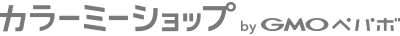憶えよ、汝死すべきを 死をめぐるドイツ・プロテスタンティズムと音楽の歴史
-

「死」という問題を、ドイツ・プロテスタンティズムにおける「神学」と「音楽」の見地から、立体的に考察。16世紀から20世紀前半までにわたる各時代の歴史的背景や政治、文化を踏まえつつ、多数の譜例や図版を用いながら展開し、テーマを鮮やかに描き出す。
【目次】
プロローグ
二つの方法論的序論
「文化の神学」の課題としての死の問題――理念史から社会史へ
1.「文化の神学」という方法
2.学問 Wissenschaftとしての文化の神学
3.本研究のための三つの根本的な要点
4.神学における諸問題を取り使った各章の概要
「音楽と死」をめぐる解釈学的省察へ向けて
1.なぜ「音楽と死」なのか
2.「音楽と死」をめぐる研究の現状
3.本書における音楽研究の方法論的前提
4.本書における音楽研究の方法論的限界
第1部 宗教改革と宗派分裂の時代(16−17世紀)
第1章 宗教改革とふたつの17世紀
――連続と断絶の間にある死の問題
1.中世に属する宗教改革とふたつの17世紀
2.中世キリスト教における死の歴史性
――ヨーロッパのキリスト教化と
キリスト教のヨーロッパ化
3.宗教改革は近代の始まりなのか、改革された中世なのか
4.16世紀と17世紀との「断絶」
――魂のアンシュタルトとしての教会から
魂の約束としての教会へ
5.16世紀と17世紀との「連続」
――宗教改革とドイツ・ルター派正統主義
6.「現象を救う」
第2章 16−17世紀における音楽と死をめぐって
1.中世末期における死をめぐる状況
2.死・来世・音楽──ガルス・ドレスラーの場合
3.「往生術」
4.ルター派の修養書
5.葬式説教
6.ドレスラーのモテットと往生術
7.宗派分裂・正統主義成立期の敬虔
8.シュッツのモテット
《今よりのち、主にありて死ぬ死者は幸いなり》
9.葬式説教にみる聖書解釈との関係
第2部 18世紀
第3章 宗教的であるが、教会的ではない死
――敬虔主義と啓蒙主義の時代の教会と神学
1.神学と教会にとっての18世紀、
あるいは「信仰の確かさ」という問題
2.フランス革命とドイツ・プロテスタントの神学と教会
3.自然に関する知識の増加の影響、
あるいは死の理解の転換
4.啓蒙主義的な思想における死の理解、
あるいは神学と音楽における死の問題
5.信仰の世俗化と世俗音楽が宗教音楽に与えた影響
第4章 18世紀における音楽と死をめぐって
1.ルター派圏における死をめぐる敬虔実践の変化
2.霊的婚姻のトポスと二つの終末論
3.J. S. バッハのカンタータ《来たれ、甘き死の時よ》
4.世俗化する死──啓蒙主義時代の死に対する態度
5.C. W. ラムラー /C. H. グラウン
《イエスの死》をめぐって
第3部 19世紀
第5章 宗教の私事化の時代における死
――19世紀の教会と神学における死の問題
1.偉大なる神学者たちの時代としての19世紀
2.「宗教の私事化」と19世紀のプロテスタント神学
――シュイライアマハーの場合
3.「宗教の私事化」と19世紀のプロテスタント神学
――「プロテスタント協会」と
「プロテスタント友の会」の場合
4.ルートヴィヒ・フォイエルバッハの問題
5.死の理解の変質
第6章 19世紀における音楽と死をめぐって
はじめに
1.英雄の死
2.愛する者の死
3.慰めと生の源泉としての追憶
4.救済/成就としての死
5.死への憧憬の音楽的表現
6.ブラームスにおける諦観と憧憬
7.シュライアマハーにおける宗教・愛・死
8.ノヴァーリスと逆転した「婚姻の神秘」
9.終末論的な愛の賛歌
第4部 20世紀前半
第7章 表現主義の時代の教会と神学
――新しい宗教性と音楽
1.1905年から1930年までのプロテスタンティズム
2.「制度としての教会」批判
3.広義の表現主義
4.表現主義という芸術運動
5.第一次世界大戦と「表現主義」における死の問題
第8章 20世紀前半における音楽と死
―― A. シェーンベルクの無調期を中心に
1.本章の課題と対象
2.タブー視される死
3.芸術宗教の展開としての表現主義
4.死と女性的なるもの
5.《ヤコブの梯子》
エピローグ/参考文献/索引
深井 智朗:著
大角 欣矢:著
A5判 上製 402ページ
出版:日本キリスト教団出版局
憶えよ、汝死すべきを 死をめぐるドイツ・プロテスタンティズムと音楽の歴史
こちらの商品が
カートに入りました
憶えよ、汝死すべきを 死をめぐるドイツ・プロテスタンティズムと音楽の歴史