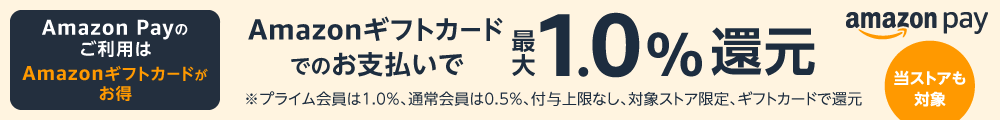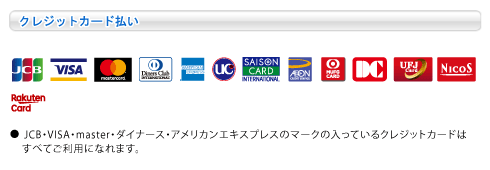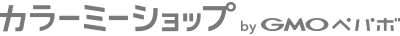生命操作と人間の尊厳
-

人生の最期をどのように迎えるかを重視して,安楽死や尊厳死を法制化する声が強まっている。また終末期を迎えるまえに,本人,家族や医療,福祉の関係者と話し合い,人生の終焉を準備することも提唱されている。
本書では,安楽死の法制化に伴う課題について海外のケースも紹介し,また死の自己決定について確認を求められる患者や家族,医師など関係者の対応,また家族の負担軽減や無益な延命治療の拒否について考察する。
「いのち」を自己決定により操作する倫理的な問題,安楽死・尊厳死だけでなく,胎児の操作や生殖補助治療など生命技術の使用と制御についても広く考える。
本論では終末期の人の権利保護を明らかにし,死の原因を哲学的に分析するとともに,ヤスパースを手掛かりに,生と死の自己決定と実存について考察する。また蘇生処置停止指示をめぐる本人の意思確認や,子どもの命と医師はどう向き合うのか,さらに代理出産など生殖技術とそれが使われる人々の現状を明らかにする。わが国のハンセン病の歴史や現実について差別と公益の観点から分析する。また急速に先端化する生命科学に対応できない倫理の問題を解明する。これらの生命操作と人間の尊厳の状況に対し,キリスト教と仏教の立場から問題の本質に迫る。映画『PLAN75』で描かれた安楽死について市民の意見を検討し,哲学科の学生と筋萎縮性側索硬化症の患者との対話により臨床哲学対話の可能性を探求する。
生命倫理から現代における多様な人間観を問うた12編。
はじめに(田坂さつき)
各章要約
1 終末期の人々の「脆弱性」と医療との関係における権利保護(建石真公子)
はじめに――終末期の患者の権利と脆弱性
1 脆弱性とはどのような概念か
1)語源に基づく一般的な内容
2)生命倫理における脆弱性の概念の登場――アメリカ,欧州評議会,EU,日本
3)脆弱性に関する二つの捉え方
2 終末期の人の権利――保護に関する法の不在という問題
1)行政的指針及び学会の指針
2)患者の権利の欠如
3 法の不在――裁判所による安楽死および治療の中止に関する合法性の法的基準の判断
1)積極的安楽死が合法となる4要件
2)医師による治療の中止は合法か――患者の自己決定権に関する判断
3)治療行為以外におけるALS患者に対する自殺幇助事件における自己決定権
4)日本における憲法上の自己決定権
4 フランスにおける「死の援助を受ける権利」法案の課題
1)2025年法案以前の終末期医療に関する法制度
2)国家倫理諮問委員会の終末期医療に関する「意見Avis」(2022年)における議論
3)終末期に関する市民会議の報告書
4)法案――権利の定義と正当化理由
5)法案――死の支援の権利へのアクセスの要件
6)法案――死の支援を受ける権利の手続き
7)法案――良心条項
8)法案――異議申し立てと監視条項・追跡可能性
9)法案――妨害罪
10)法案の課題――患者の脆弱性および緩和ケアの不十分性
結論にかえて――日本の終末期法制における「脆弱性」への配慮と民主的プロセスの必要性
参考文献
2 「死に方」の諸相をめぐる哲学的覚書――「死因」概念を軸に(一ノ瀬正樹)
1 生きとし生けるもの
2 死の情景――と殺と死刑
3 死の情景――獣害と孤独死
4 「死因」による「死に方」の分類
5 反事実的条件分析の迷路
6 「死因」概念は機能するか
7 安楽死と孤独死
8 自然死と非意図的「死に方」
9 結果としての「死」
10 私たちはいつも死んでいる
参考文献
3 生と死の自己決定と実存(Existenz)――ヤスパース哲学を手がかりとして(羽入佐和子)
はじめに
1 自己決定の場面
2 ヤスパース哲学における「Existenz(実存)」
1)自己と「実存」
2)「限界状況」と「死」
3)実存と交わり
3 医師と患者との関係
1)『精神病理学総論』における「人間存在の全体」
2)医師と患者の関係と「実存的交わり」
4 「失われつつ在る自己」と「生きて来た自己」
1)「実存」の歴史性
2)「失われつつ在る自己」
3)決断の場面と実存の決断
むすび
4 DNAR指示とACP,問題点を考える(香川知晶)
1 DNAR(蘇生処置停止)指示,ひとつの事例
2 DNRからDNARへ,米国の場合
1)CPR(心肺蘇生術)の登場
2)CPRの問題点とDNR(蘇生処置停止)指示
3)DNR指示をめぐる疑念とガイドライン
4)DNRからDNARへ
3 日本におけるDNARの現状
1)日本のDNR理解
2)DNAR指示誤用の現状
4 DNARと日本の「尊厳死」
1)DNARからAND(自然死許可)へ
2)DNARと日本の「尊厳死」
3)滑りやすい坂,DNAR指示とPOLST(生命維持処置に対する医師の指示書)
5 救急の場面におけるDNARの現状
1)救急の場面におけるDNAR,問題の背景
2)救急場面での対応,運用の細部
6 終末期医療と本人の意思:リビングウィル・ADからACPへ
1)「死ぬ権利」と「自然死」・PAS(医師幇助自殺)
2)リビングウィル・ADからACP(アドバンス・ケア・プランニング)へ
3)モリソン・ショック
7 何でもACP症候群の周辺
1)日本におけるACP
2)「人生の最終段階」とACP
3)社会保障制度改革とACP
4)「自助,共助及び公助」
8 本人の意思という問題
5 子どものいのちを前に,医師であるわたしは何を要請されているのか(笹月桃子)
1 問い
2 子どもの脆弱性
3 傍観者・加担者にならないために
4 子どもの生命維持治療の中止をめぐる議論
5 子どもの「いのち」をめぐる諸概念について
6 Prf. Dominik Wilkinson の主張
1)慈しむ対象としてのいのちの価値,生きることの利益とは何か
2)Suffering「苦痛」
3)二項対立を避ける底上げ的なベクトル
4)協働関係の在り方
7 当事者とは何か
8 他者として畏れを抱く
9 社会は医療に何を求めるのか,医療は社会に何を託すのか
10 そしてわたしは
11 謝辞
参考文献
6 消され・声をあげ・立ち上がる:生殖技術に利用される人々の不可視化と抵抗(柳原良江)
1 生殖技術の利用をめぐる議論のありかた
2 基本枠組みの構築
3 グローバル市場の形成と拡大
4 支配的な声
5 依頼者による権利主張
6 封じられた声
7 表面化しない声
8 届かない声と作られる声
9 「生まれる人」の不可視化
10 市民運動による抵抗
1)表面化する問題
2)活動家による批判論の高まり
11 女性団体による抵抗
1)欧州左派の組織化
2)国際的な連帯
12 英国女性たちの運動
13 党派を超えた運動
1)保守派の生殖技術批判
2)当事者がつなぐ連帯
14 禁止法への動き
15 国際社会における呼びかけ
16 今後の議論の在り方に向けて
参考文献
7 差別と公益――ハンセン病をめぐる倫理的考察(小島優子)
1 生殖に対する権力の関与
2 ハンセン病に関する隠喩
1)懲罰としての病いの隠喩(古代),および軍事的隠喩(近代)
2)日本における穢れの隠喩としてのハンセン病
3)近代におけるハンセン病と社会
3 スティグマについて
1)スティグマとは何か
2)スティグマと差別
4 優生保護法と人間の尊厳
1)子供の引き取り手に関する問題
2)体質遺伝に関する議論
3)ハンセン病患者への断種について
5 ハンセン病患者に対する二重の差別
6 生命に対する自律
8 生命科学テクノロジーをどう制御するのか?――「倫理が間に合わない」時代の倫理を問う(島薗 進)
はじめに
1 生命科学テクノロジーは人類に何をもたらすのか?
1)ブタの心臓の人体への移植
2)異種臓器移植実現への情熱
3)ノーベル賞受賞者が見た悪夢
4)恐れられるヒト生殖系列ゲノム編集
5)ヒトゲノム編集国際サミット
6)ヒト胚ゲノム編集の境界線をどこで引くか
7)恐れられている事態と規制案の欠如
8)独立の学際的で多元的な倫理委員会
2 生命を人工的に創造する新たな科学
1)“神の領域”への挑戦?
2)バイオテクノロジーの希望
3)解析生物学と合成生物学
4)合成生物学の第一のルート
5)遺伝子工学からゲノムテクノロジーへ
6)合成生物学の牽引者たち
7)合成生物学がもたらすものへの懸念
3 現代科学技術の制御の困難
1)科学的合理性の視野狭窄
2)想像はできるが予想はできない破局的事態
3)黙示録的な事態と賢明な破局論
4)破局を招く聖なるものと暴力
5)悪の不可視性
6)操作可能なものの内だけの思考
7)思考の欠如と悪の陳腐さ
4 現代科学技術文明のはらむ暴力性とその制御
1)哲学的問題としての現代科学技術文明の制御困難性
2)核抑止論の合理性は確かなものか
3)抑止論の基盤の弱さと暴力論
4)比較宗教論的な視座からの問い
5)現代的な「暴力の制御」思想と宗教伝統
6)主体性を重んじる近代がもたらす脱倫理
参考文献
9 生命操作と人間の尊厳――現代キリスト教思想の議論から(芦名定道)
1 人間の尊厳と神の像
1)「人間の尊厳」の問いとキリスト教
2)キリスト教思想史研究から
2 クローン技術をめぐるキリスト教思想
1)論争中の遺伝子工学:その光と影
2)ヒトクローン論争:三つの立場
3)人間の尊厳をどう論じるか
4)「神の演じる」を吟味する
5)第一原因としての神
6)創造された共同創造者
7)楽観主義を修正する
8)楽観主義を修正するキリスト教的な視点としての「贖い」
9)創造と共同創造に登場する隠喩表現についての議論
3 関係概念としての人間の尊厳
1)人格と双子問題
2)関係性としての人格・尊厳
3)関係性としての「神の像」
4)子どもをデザインすることの倫理的問題
5)被贈与性の倫理
4 おわりに
10 仏教における自死――三名の比丘の自死を巡って(鈴木隆泰)
1 仏教において自死は容認されているのか
2 自死した三名の比丘
3 自死は殺生の罪を犯したことになるのか
4 四諦
5 仏教における「解脱した者」のありかた
6 仏教徒――自利行と利他行に励む者
7 三人の比丘の自死を通して見る,仏教における安楽死・尊厳死
参考文献
11 『PLAN75』シネマカフェ参加者 アンケートから見る課題(波多野真弓)
1 アンケート調査の概要
2 アンケート調査――分析方法
3 アンケート調査結果――映画「PLAN75」を見て
4 KH coder による計量テキスト分析
1)自由記述「大いに変化した」「変化した」「少し変化した」
2)映画『PLAN75』を観て考えたこと――立正大学哲学科臨床哲学履修生
3)シネマカフェから考えたこと――立正大学哲学科臨床哲学履修学生
5 安楽死制度に関わる諸問題
1)生命の価値の軽視
2)社会的・経済的圧力による強要リスク
3)制度の強制力の増加
4)終末期ケアや緩和ケアの軽視
5)社会保障制度への影響
6 哲学カフェの有用性とまとめ
引用・参考文献
12 安楽死を考える臨床哲学(田坂さつき)
はじめに
1 講義科目「臨床哲学」
2 週外科目「体験学習」
1) ALS患者宅訪問
2) 臨床哲学実習
3 2023年度卒業論文
4 2024年度臨床哲学実習
参考文献
あとがき
執筆者紹介
索引
田坂 さつき 編
出版年月日 2025/10/15
ISBN 9784862854490
判型・ページ数 菊判・366ページ
知泉書館
生命操作と人間の尊厳